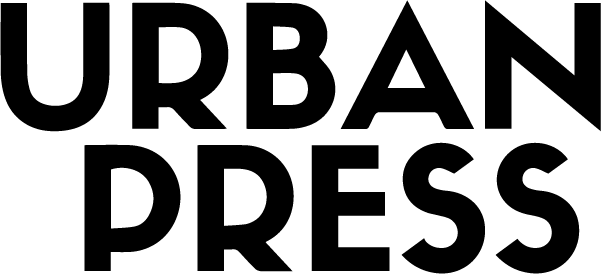厳しい冬が去り、暖かく過ごしやすい季節になるにつれ、行事やお祝い事も増えてきます。お祝い事には、お祝いの気持ちを込めて贈るご祝儀がつきものですよね。
中身が入っていればそれで十分、ご祝儀袋なんてなんでもいいやと思う方も中にはいらっしゃるかと思います。ですが、大切な人を思う気持ちとは、どんなもので渡すかを考えるところも含んでいると感じます。
たかがご祝儀袋、されどご祝儀袋。―こだわったご祝儀袋にすることで贈る気持ちを特別にし、心に残る贈り方ができます。受け取る側も気持ちが上がること間違いなしです。
また近年、商品選択にはSDGsのようなサスティナブルな視点が重要視されています。
そこで今回おすすめしたい、木のご祝儀袋についてご紹介致します。話題になるだけではなく、環境に配慮しているので必見です。
国産杉のご祝儀袋
国産杉の間伐材や端材を活用し製品化された、環境への配慮とデザインが両立した次世代型のご祝儀袋です。
販売を行う木KORABOの商品の特徴は、間伐材や端材など本来捨てられてしまう部分を使用し産地の分かる国産材にこだわった商品を扱っています。
今回ご紹介する木のご祝儀袋の魅力や特徴をまとめました。
おすすめアイテム
温もりを感じる香り
一番の魅力は何と言っても、香りです。商品を手にした際に広がる杉の木の香りに癒されます。香りは、爽やかさの中にどこか懐かしさを感じます。この香りに感じる懐かしさには、西日の差し込む教室や自然豊かな森に囲まれた音楽堂を連想させるような温もりを感じます。そして、長く香りを愉しめるご祝儀袋は中々世に見かけません。見て触れて、それに加え香りを愉しむことができる、これは推しポイントです。
品質へのこだわり
江戸時代から林業が盛んで、有名な杉の産地である大分県産杉で作られています。大分県産の杉はほんのり赤みがかった優しい温もりを感じる色合いが特徴です。
質の良さは、何と言っても、職人の技が光る製材・加工過程にあります。単板(薄くスライスされた木材)をしっかりと乾燥させ製品化されている為、持ちが良く長く愛用できます。また、薄くスライスした杉材に曲げても割れにくいラミネート加工という特殊加工を施している為、丈夫なのにしなやかな質感です。
熟練の職人さんがひたむきに、一つ一つ丁寧に作業し作られています。その為、杉本来の良さを保持した状態で私たちの手元に届くことができるのです。
環境に優しいものづくり
木を育てていく過程で生まれる、本来ならば捨てられてしまう間伐材や端材などの部分を有効活用し製品化されています。また国産材にこだわり活用することで日本の豊富な森林資源の活用やCO2の排出削減に貢献しています。
奥ゆかしい伝統的なデザイン
七宝模様や松竹梅といった日本の伝統文様が施されています。七宝模様や松竹梅は、おめでたい場面で用いられることが多く縁起が良い吉祥文様として知られています。日本の伝統文様は、和を感じる杉と非常に馴染みます。控えめながらも慎み深い上品さと心遣いを感じる落ち着きのあるデザインです。また、自然が織りなす色合いや木目は人と被ることがなく、シンプルで可愛らしいデザインでもあります。その為、幅広い世代におすすめです。
おしゃれなご祝儀袋を引き立てる袱紗(ふくさ)
ご祝儀袋をついつい直前になって急いで準備するということもよく耳にします。また、折角素敵なご祝儀袋を用意しても、そのままでは準備不足で不十分。ご祝儀袋などの金封を持参する際、袱紗に包むことがマナーですよね。準備にも気持ちにも余裕を持って当日を迎えたいものです。
そこで、準備が愉しくなる、ご祝儀袋に合わせた袱紗選びを提案します。おしゃれなご祝儀袋に合う袱紗をファッション感覚で選ぶことで、準備を愉しんで頂きたいです。
袱紗(ふくさ)とは
贈答の為の金品を包んで持ち運ぶ為に使用するものです。その理由として、金封に傷や汚れがつかないようにすることや贈る相手への敬意や祝意を表し、礼儀を尽くすことが挙げられます。金封がむき出しのままではなく、袱紗を使い贈り物を丁寧に扱うことで相手への礼儀を尽くすことができます。
袱紗(ふくさ)の種類
袱紗には、大きく分けて【挟むタイプ】と【包むタイプ】があります。
挟むタイプの袱紗
金封袱紗
長財布やクラッチバッグのような形状で、開いてご祝儀を挟むタイプの袱紗です。包む必要がなくご祝儀の出し入れがしやすいのが特徴です。
包むタイプの袱紗
・風呂敷袱紗(手袱紗)
一枚布で包む風呂敷タイプの袱紗です。こちらは、正式な袱紗とされています。使用後はそのまま折り畳める為、場所を取らずコンパクトで便利です。
・爪付き袱紗
風呂敷タイプに爪がついている袱紗です。端にフリンジや留め具の爪がついている為、バックの中で包みが開くことなく取り出しやすいです。
・台付き袱紗
包みの内側に金封をのせる台が付いた袱紗です。台があることで、金封がずれることなく綺麗に包むことができ、型崩れしにくいのが特徴です。また、台の部分には、金封を固定するゴムや紐が付いているものが多いです。さらに台が慶弔どちらにも対応できるようリバーシブルになっていることが多いです。
袱紗(ふくさ)の色選び
シーンに応じた袱紗の色選びやマナーを踏まえた上で、ご祝儀袋にぴったりな袱紗のカラー選びを愉しみましょう。今回ご紹介している木のご祝儀袋を参考にご紹介致します。
慶事向け
ご祝儀袋など慶事向けには、明るい暖色系で柄のない無地を選ぶのが基本です。具体的には、赤やピンク系、オレンジやベージュ系、黄色や金色などが挙げられます。また、紫色は慶弔両用カラーの為、袱紗のカラーで迷うことがあれば濃い紫色をチョイスすると◎です。
また、柄入りの場合は派手過ぎないものがおすすめです。結婚式などの慶事では、松竹梅や鶴亀など縁起の良い柄が入っているものを選びましょう。
弔事向け
寒色系である青系・緑系・グレー系などの沈んだ色は、弔事用になります。中には、寒色系であっても刺繍やビジューが付いた華やかな袱紗もあり、慶事に使用できるものもあります。
色選びを愉しむ
今回ご紹介している木のご祝儀袋は、杉特有のほんのりとした赤みや優しい自然の木の色合いが映えるカラーを選ぶと◎。中でも、高貴で慶弔両用である紫色や藤色は和を感じる杉に非常に合い粋な装いになります。また、施されているデザインに近い赤色や朱色のような黄みを帯びた赤も程よい華やかさが出て映えます。このように、合わせるカラーを変えるだけで、印象やイメージがガラリと変わります。大切な人のイメージに近い色を想像しチョイスするのも個人的にオススメです。
幸せのリサイクル―ご祝儀袋のその後
ご祝儀袋を受け取った後にどう扱うか、迷う方は多いようです。
気持ちのこもったご祝儀袋を手放すにも、最後まで丁寧に扱いたいものです。
そこで、ご祝儀袋のその後の素敵な活用方法をいくつかご紹介します。
栞(しおり)
お好きなデザインや木目部分を作りたい形やサイズにカットすると、栞になります。お気に入りの本や読みかけの書物に挟むと気分が上がります。紙とは違い、丈夫で折曲がりにくくシワになりにくい為長く愛用できます。
箸置き
水引の結び目の部分だけをカットし、お箸が置きやすい形に整えるだけで簡単に箸置きに早変わりします。最後にニスを塗って仕上げると、防水性や耐久性が増します。口に入れるものが触れても安心な、食品衛生法適合ニスを使うのがおすすめです。おめでたい日や家族が集まる際に、置くだけで食卓が華やかになります。
葉書、メッセージカード
お好きな絵柄や木目部分を作りたい物のサイズにカットするだけです。また、ラミネート加工により木の質感が滑らかな為、メッセージを記入する際は、油性ペンで書くことをおすすめします。
年賀状やメッセージカードとして贈り物に添えると、一味違った記憶に残る贈り物になります。贈ったご祝儀袋が別の形で違う大切な人に贈られる。まさに幸せのリサイクルですね。
最後に
木KORABOの商品を手にした時に感じたことは、経年変化を愉しめるということです。
“経年変化”とは物質が時間と共に変化していくことで、年月の経過とともに品質や性能が悪くなる状態 の“経年劣化”と同等に用いられることが多く、少々ネガティブなイメージを持たれがちです。保管状態にもよりますが、どんなものでも、時間と共に変化していきます。 “経年変化”というマイナスイメージを払拭するような、寧ろ変化していく経過を愉しみ歳月とともに風合いが増していく様子に愛おしささえ感じることができるように思います。
環境変化や時間変化によって日々変化していく過程が、まるで木が生きているかのようで、木を育てていくような感覚に感じます。そしてそれが、過ぎ行く毎日の尊さに気づかされ、その一瞬一瞬を大切にしたいとさえ感じてしまうような気がします。これが愛おしさに繋がるように感じます。このなんとも言えない温もりや愛おしさは、木KORABO商品の特徴です。是非一度手に取って触れて感じて頂きたいです。